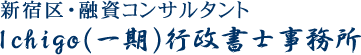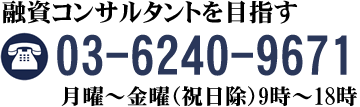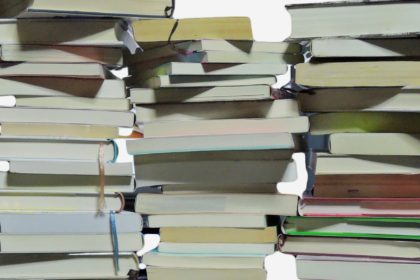信用保証協会の保証制度の見直しについて【その2】

こんにちは、行政書士再生コンサルの引地です。
前回は、新たに信用保証協会の保証制度の見直しが平成30年4月1日より
行われるということと、その概要についてご説明しました。
そしてその中でも、特に4つの改正点が私たちの生活に大きく影響する
のではないかということについてもお話しいたしました。
そこで、今回はこの中で特に影響が大きいと思われる4項目について、
細かく解説したいと思います。
1.小規模事業者への支援拡充(特別小口融資枠の拡大)
現在、信用保証協会つき融資の一つとして行われている「小口融資」の
限度額が1,250万円→2,000万円に拡大されます。
※ 特別区小口融資
従業員20人(商業・サービス業では5人)以下の企業を対象に
1,250万円を限度として行われている融資制度。
この小口制度は責任共有制度の適用を受けないため、比較的、借りやす
い融資としてこれまでも多く使われていましたが、この改正により、
さらに上限が広がり、使い勝手がよくなりました。
ただし、今回の改正の2,000万円の上限については、他の信用保証協会付
融資の残高を合計してカウントされます。
したがって、現在すでに500万円の信用保証協会付融資の残高がある場合
にはそれを差し引いた1,500万円までしか利用できないことに注意が必要
です。
2.特定経営承継関連保証の創設
事業承継を一層促進するため、法の認定を受けた中小企業の代表者個人
が承継時に必要とする資金 (株式取得資金等)を信用保険が対象とする。
中小企業等が事業の承継を受ける際には、代表者などから株式を取得し
たり、また、相続による場合には相続税の支払いをする必要があります。
しかし、これまでは後継者個人による株式取得資金や、事業承継に伴う
相続税・贈与税に対しては、後継者個人が事業を行っていないことを理
由に融資の対象外とされていました。
そのため、多くのケースでは株式の売却金をそれらの資金に充てるなど
が避けられず、株式の分散を招くこととなっていました。
しかし、この改正により事業を営む会社を承継した代表者が必要とする
株式等の取得金や事業用資産の取得金、事業用資産に関する相続税・贈
与税の納税資金、事業継続に必要な資金などについて最大2.8億円の融資
を受けることが可能となりました。
ただし、この適用は誰でも受けられるというものではなく、
「事業承継に伴い、事業活動の継続に⽀障が⽣じているとして、
経済産業大臣の認定を受けた中小企業の代表者個人のみ」
が対象となります。
3.円滑な撤退支援
経営者が撤退を決断する場合に必要となる資金(買掛金決済、原状復帰
費用等のつなぎ資金)の調達が円滑に行えるよう、新たな保証メニュー
が創設されます。
先行きの見通しが立たず経営者が自ら廃業を望む場合には、一定の要件
の下、廃業に必要となる資金の調達が円滑に行えるよう信用保証協会が
保証をする制度となります。
この制度を利用する場合には、次の要件を満たす必要があります。
ア 事業譲渡や経営者交代等による事業継続が⾒込めず、⾃ら廃業
を選択する者
イ 直近の決算が実質的に債務超過でなく、完済が求められる債務
について事業清算により完済が⾒込めること
ウ バンクミーティング等により合意に⾄った廃業計画書に従って
計画の実行及び進捗の報告を行うもの
しかし、実体的に考えた場合、廃業をする場合には相当の負債を抱えて
いるケースが多いと考えられ、「実質的な債務超過でない」という要件
を満たせる企業はほんの少数しかないのではないかと思われます。
また、通常、廃業に伴い収入も見込めなくなることから、その後の返済
のめどがつかないといった問題もあり、その場合、この制度自体が絵に
描いたモチとなってしまう可能性が考えられます。
4.信用保証協会と金融機関の連携
信用保証協会と金融機関との連携を法律上に位置づけ、中小企業のそれ
ぞれの実態に応じて、プロパー融資(信用保証なしの融資)と信用保証付
融資を適切に組み合わせ、信用保証協会と金融機関が柔軟にリスク分担
を行っていく。
また、その実効性を担保するため、信用保証協会向けの監督指針にもリ
スク分担について明記し、各信用保証協会・各金融機関のプロパー融資
の状況等について情報開示を行うとともに、モニタリングを行います。
これは、これまで高い割合で信用保証協会付融資に依存していた体質を
今後は民間金融機関からの資金(プロパー融資)に徐々に切り替えてい
こうというものです。
また、これを実施していくうえで
・信用保証協会別
・金融機関別
・信用保証協会ごとの金融機関別
という3つの区分から表の作成をし、具体的なプロパー融資等の割合を
モニタリングしていくものとされています。
しかし、通常の中小企業においては、その大半が経営基盤がぜい弱であ
るため、国の制度である信用保証協会付融資に頼らざるを得ない面があ
ります。
また、プロパー融資では、担保・保証が前提となるため、この手当てが
できない企業についてはプロパー融資も信用保証協会付融資も受けられ
ないといった事態も想定され、国による不採算企業の撤退推進と相まっ
て、厳しい選択が求められるものと思われます。
とはいえ、制度として決まってしまったことである以上、これに沿った
運用がされるのはほぼ間違いないでしょう。
以上のように今回の見直しでは、これまでと比べて緩和される部分があ
る一方中小企業に対する目付が厳しくなっている部分もあります。
したがって、今後、中小企業としては、いままでのような金融機関と対
立する構図ではなく、
・ 金融機関と連絡を密にとりあい、情報提供をしていく。
・ 経営改善計画を作成し、これを金融機関と共有してその経営状況
を透明化する。
といった対応を積極的に行い、金融機関の信頼を獲得していかなければ
ならない状況になると思われます。
もっと融資や行政書士の仕事について知りたいと思ったあなたは、ぜひ融資コンサルになるための特別無料レポートを請求して下さい。
ブログには書けない特別な情報をお送りいたします。
関連ブログ
-

決算書の超簡単な見方とは? 【その2】
2019年10月18日
ブログを読む -

行政書士のための融資講座(その10 設備資金)
2020年02月26日
ブログを読む -

行政書士のための「融資講座」【その2 融資の種類1】
2019年10月21日
ブログを読む -

補助金と行政書士について【その2】
2017年05月15日
ブログを読む -

行政書士のための融資講座(その11 保証人)
2020年02月27日
ブログを読む